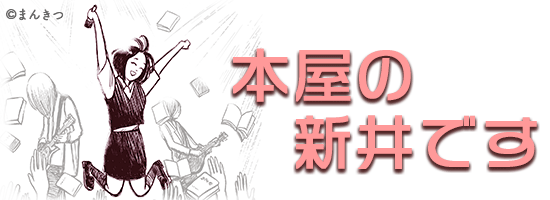急に秋めいた日の午後、私は新宿のはずれにあるビジネスホテルにいた。かき氷屋が開店したと聞いて、とりあえず予約の時間に来てみたのだが、勝手がわからない。ロビーに人待ち顔で佇めば、まるで訳ありの人妻だ。
するとタブレットを持った白衣の男性が現れて、小さなバースペースに案内してくれた。かき氷屋によくある、間借り店舗だった。もうひとりの男性だけが氷を削り、最初の彼は配膳を担当している。しかし、どうも 手つきが覚束ない。
怖々と盆ごと提供された、葡萄のエスプーマとラベンダーのかき氷は、ありがちな秋のデザートと一線を画し、繊細さが感じられた。舌が冷えてきた頃、温かいコンソメスープがサービスで提供される。インスタントではない、素朴で丁寧な味で、思わずおかわりをしたほどだ。
食後の雑談で、実は白衣の男性こそがシェフであり、お客の反応が気になって、休みの日にこうして店に立つこともある、と聞いた。そりゃコンソメまで美味しいわけである。
作家が慣れない手つきで書店のレジに立つような感覚だろうか。その場で食べてもらえるかき氷のようにはいかないが、いざ読者を目の前にすれば「いかがでしたか?」と直接訊ねたくなるのかもしれない。
(新井見枝香/HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE)
(本紙「新文化」2021年10月28日号掲載)