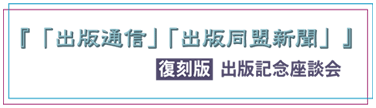小社では、2001年12月に「新文化」創刊50周年記念事業として、「新文化」の前身である『出版通信』(1933年~39年)、『出版同盟新聞』(1940年~43年)を、『「出版通信」「出版同盟新聞」復刻版』として復刻しました。(※絶版になりました)
この座談会は、刊行に際し、ご協力を頂いた3氏に復刻版と戦前・戦中の出版界について語ってもらったものです。なお、この座談会は復刻版第1巻にも収録しています。
初掲載:2001年12月
<座談会出席者> ※座談会出席者の肩書きは当時のものです
植田康夫氏(上智大学文学部教授・日本出版学会会長)
小林一博氏(出版評論家・元「新文化」編集長)
吉田則昭氏(立教大学大学院博士課程・日本出版学会理事)
創業者 丸島誠の人となり
吉田: 昭和五年に『出版通信』が創刊されたということですが、創業者丸島誠さんの人となりにつきまして、小林さんからお話し願いませんでしょうか。
小林: 丸島誠さんは、私が一九七二年の九月に<新文化>に編集長で入社したときには社長として頑張っておられました。入社するときの条件が、「紙面については一切まかせましょう」ということでした。まかせるという言葉通り、紙面づくりについては一切文句をいいませんでした。
当時の<新文化>は、一面が広告と新聞の業界で、二面以下が出版業界という紙面構成でした。ちょうどブック戦争が始まったため、毎週一面で正味問題を特集として取り上げておりましたが、十月の中旬に書協と日書連が妥協し、書籍の正味を二%引き下げるという形でいったん終結しました。その直後に、「もうブック戦争は終わったのですから一面を元に戻してくださいと言われたました。しばらくこのままでやらせていただけませんか」と申し上げましたところ、当時専務の丸島日出夫現社長によるバックアップもあり、受け入れていただき続投ということになりました。
それにはエピソードがありまして、後日、読売新聞の関係者に聞いたところでは、当時の務台光雄社長から「最近<新文化>がおもしろいではないか」といわれたらしいのです。丸島社長は務台さんとは戦前からのおつきあいがありましたから大きな力となったのでしょう。
紀伊國屋書店などの取材も戦前からの太いパイプがありましたから、必ず自身で行っておられました。取材から帰ってくると、その場で原稿を少し癖のある字で鉛筆でわら半紙に書いておりました。そのころ六十五、六歳になっていたと思いますが、本当にまじめな人柄でした。それは亡くなるまで一貫しておられました。外に対しても内に対しても、誠実な対応というのは、たぶん中学を卒業して永代静雄さんの新聞研究所に入ったときから一貫して持ち続けていたのではなかったのでしょうか。今回復刻にあたり改めて『出版通信』を読み、丸島誠さんの性格がそのまま表れた新聞だと感じました。
『出版同盟新聞』について言えばこれは、丸島誠さんと帆刈芳之助さんの共同作品といえます。二人の関係は帆刈さんの方が年上で、丸島さんは帆刈さんに非常にかわいがられていたようです。ただ、ジャ-ナリストとしては二人は対称的ともいえます。帆刈さんという人は思想的・理論的な記事を得意とするいわゆる論客です。丸島さんももちろん主張や論説も書かれてはおりますが、むしろ客観的な報道を重視し、フィ-ルドワ-ク的な取材が得意だったのではないでしょうか。その点でも資料が少ない戦前戦中の出版界を解明するための一次資料としての価値があるのではないでしょうか。
植田: どのような経歴の方なのですか?
小林: 中学生の頃から新聞記者にあこがれ、中学を卒業後永代さんの新聞研究所を訪ねていったら採用してくれたそうです。誠実な人柄のうえ文章力があったからでしょう。昔の中学生ですから十七歳です。当時としてはたいへん高い給料をもらったそうです。
自分のことはあまり語りたがらない方でしたので永代さんのことなどを聞いたことはほとんどありません。もったいない話です。聞いておけば良かったなと思っています。今の社長も嫡男なのですが父親とはそういう話をしていないようです。亡くなって改めて「親父は偉かったな」とか「清潔だったんだな」とか、、「もう少し財産を残してくれたら俺たちは苦労しなくてすんだのに」といういい方をしていたことがあります。(笑い)。ほとんど話をしなかったようです。
一つには、戦争に対して協力し、時局に妥協したという自責の念があったのではないでしょうか。私などが時々話題にしても、「あ、それはこうだったよ」と一言しかいわないのです。『出版通信』などを読むと記事にされており、良く知っているはずなのですが、背景説明等は全然してくれないのです。だいたい業界紙をやっている人間というのは、べらべらと話す人が多いのですが、そういう部分はありませんでした。
『出版通信』を支えた戦前の出版界
吉田: 『出版通信』に掲載されている広告を見ますと、それも戦前の貴重な資料だと思いますが、量的にも多く業界全体がこの新聞を支えていたのだということがわかりますが、当時の出版業界について、時代背景について植田先生からお話しいただけますでしょうか。
植田: 私も今回『出版通信』と『出版同盟新聞』のコピ-を読ませていただき、改めて戦前の出版はどのようなものだったのかということについて考え直してみました。結局、戦前の出版界、あるいは現在の出版界もそうなのですが、そもそも日本の出版界の特色というものをさかのぼりますと、やはり明治期にいきます。
日本の出版史というのはヨーロッパなどに比べて少し不幸な事情があり、近世から近代にうまくつながっていない面があります。書籍出版については、江戸時代までに商業出版としてきちんとしたシステムが出来ていたのです。本屋という形で出版もやりかつ卸、小売もやってしまうという形で商業出版を行なっていたのです。これはこれで良いシステムだったと思います。
明治期に雑誌という新しい媒体ができたとき、出版のシステムが変わってしまったのではないかという感じがします。明治以降は雑誌というものが非常に大きな存在になっていったと思います。講談社、中央公論社、小学館、新潮社等、明治以後発足した出版社で現在も続いている大きな出版社というのは、みんな雑誌出版社として出発しています。
つまり雑誌を発行して、それから後に単行本を出すという形でやっています。雑誌というものが非常に大きな存在になり、雑誌をうまく流通させるシステムとなってきたのです。これは実に良くできたシステムで、欧米よりも進んでいると思います。欧米では今でも雑誌は書店では売らずに、マガジンショップやニュ-ススタンドで売るかダイレクトメールという形で送るのが大部分です。
ところが、日本の場合には雑誌も書店できちんと売っています。そういうシステムを明治のころに作り、そのままずっと今日まで続いているのです。結果として書籍の方がはじかれてしまったという感じがします。雑誌の流通ルートに、何かお添えもののように書籍が乗っているように思われます。
そういうシステムを作る上で非常に大きな力を発揮したのが、明治二十年に創業した博文館です。博文館の創業というのは、近代出版史を語る上では非常に大きな存在だと思います。博文館もまた雑誌から出発しています。さらに博文館は自社で作った雑誌を流通させるために、全国の書店を組織化し、やがて東京堂という取次会社をつくりました
日本の近代出版というのはシステムの面では、雑誌を中心にして成り立ったという事情があるのです。そのような流れの中で、大正末から昭和初期にかけて、今度は出版のマス化という現象が生じます。そのときも、やはり非常に雑誌的な出版物が大量化を進める上で大きな役割を果たします。
まず第一は、改造社が大正十五年に『現代日本文学全集』を刊行し、これが三十六万部の予約をとり、昭和二年に新潮社が『世界文学全集』で五十八万部という予約登録者を獲得します。考えてみると、全集というのは書籍の形ではあるけれど、ある意味では定期刊行物です。単行本ではなかったのです。定期刊行物としての全集というものを大量に発行していくという日本独特の全集のようなものを作り出しました。
同時期の大正十四年一月に、講談社が『キング』を創刊します。これが、いきなり七十四万部という大量部数を獲得しました。大正末から昭和初期にかけて、出版の大衆化、マス化ということが顕在化します。
先ほど博文館の果たす役割が大きかったと申しましたが、もう一つは実業之日本社だったと思います。実業之日本社が明治四十二年に『婦人世界』という雑誌で委託販売制というものを作り出しました。この委託販売制というシステムをうまく使ったのが『キング』だったと思います。
キングが七十四万発行できたというのは、やはり委託販売セールスというシステムを使った成果だと思います。明治に作られた大量出版のためのシステムが完成したのが、昭和初期ではなかったかと思います。『出版通信』が創刊された昭和五年とはそのような時代であったと思います。
小林: 丸島誠さんについてもう少し話しますと、『出版通信』創刊の二年後に『である』という雑誌を発行しています。十号ほどで廃刊したようですが、堀内敬三・徳川夢声・古川緑波などが編集同人で、編集部には久江京四郎・森岩雄が在席しているという、モガモボ全盛時代の“銀座調”がベ-スの映画・音楽・漫文誌です。紀伊國屋書店の田辺茂一さんとは生涯非常に親しかったことなどを考え合わせますと、彼の知的ネットワ-クが見えてくるような気がします。
『出版通信』への期待とその報道姿勢
吉田: 植田さんが先程お話しになられましたことに関連しますが、昭和初期にも出版社の格差というものがあったわけですが、戦時に企業統合するときに、この格差が解消されるのでしょうか。
小林: 昭和五年ぐらいというのは講談社は伸びてきていますが、まだ業界をリードする立場ではありませんでした。創業者の野間清治さんも自分の会社を大きくすることに全力を傾けていた時代です。業界トップの博文館は看板雑誌の『太陽』は昭和二年に廃刊していますが、オーナーの大橋新太郎の財力の点からも、昭和十年代まではまだ博文館が業界のリーダーです。実業之日本社の増田義一さんなども、政治家志向が非常に強かったということもあって、業界のリーダー的存在の人でした。
植田: 講談社の社史では、講談社が業界で認められたのは大正十一年の関東大震災のときだと書かれています。『キング』を出そうとして準備したスタッフを急遽『大正大震災大火災』の刊行にあてるわけです。それで、四十万部の本を出して売れ、認められたといっています。
小林: 博文館についていえば、東京堂が四大取次の中でもダントツの取次でしたが、これは完全に博文館の系列会社です。博文館と東京堂の卸部の力が、やはり業界の中で厳然たる勢力を持っていて、ほかのところは下手な口出しはできなかったという時代だったと思います。そのわりに『出版通信』には博文館の記事が少ないのです。
植田: そうですね。
小林: 大橋新太郎さんを敬遠されていたのかもしれませんね。権力に近寄らずということかもしれません。
吉田: 当時の四大取次という流通システムのなかで、出版社により扱いの違いというものはあったのですか?
小林: 四大取次は雑誌が主力です。日本雑誌協会、東京雑誌協会に属する版元の雑誌は、四大取次以外では扱えなかったのです。『キング』をはじめ、『主婦之友』『婦人倶楽部』という発行部数の多い雑誌は雑誌協会の会員社の雑誌です。しかも、書店は組合に入っていなければ雑誌協会会員社の雑誌は扱えなかったのです。紀伊國屋書店は昭和二年に創業するのですが、この規定のために雑誌を扱えなかったのです。田辺茂一さんは同人雑誌の販売を積極的に進めたため、量的には多くありませんが、一つの評価を作ったということができます。
植田: 昭和十二年刊行の『書店読本』によると、戦前には書籍専業店という書籍しか扱えない書店がありました。文具を一緒に売ったり、雑誌を扱えたりと、書店も区分されていたようです。
小林: 書店のことをいいますと、昔は教科書を扱えないような書店というのは、二流、三流の書店だという位置づけがあったのです。教科書を扱っている書店というのは殿様です。経営的にも安定します。教科書を扱い、四大取次を通じて日本雑誌協会の会員社が発行する雑誌を扱っている書店というのは、安定している書店だという位置づけをされていました。書籍しかやっていないのは、大したことがないということです。書籍が大したことがないということではなく、お店の販売力や信用という面です。
吉田: 『出版通信』には内務省の納本情報がでています。あれは納本義務があるからなのですね。『出版通信』と『出版同盟新聞』の区切りとしては、出版新体制以降は権力との関わりができて、当局と一体なのだというような言われ方がなされてきています。
小林: 内務省納本リストが出ているのは、明治二十六年の出版法以来、もっとさかのぼれば明治二年の出版条例付録以来の検問、納本義務のようなものが法令化され、検閲、納本が義務づけられていたからです。当時はそれを当たり前に受け止めていたのでしょう。『出版同盟新聞』ということになってくると、統制時代に入りますし、昭和十二年には日中戦争が勃発して軍部による戦争指導も強化されますので、業界紙の当局に対する対応も違ってきているのでしょう。昭和五年に『出版通信』を創刊したというのは、出版業界が円本時代の競争に疲れて、大量の返品をかかえて、大きく転換を始めた時期ということも関係していたのではないかな。昭和五年頃の出版界は円本ブームが一気にしぼんで、本当に青息吐息のデフレ経済の時代でしたね。
植田: 本当にそうですね。『出版通信』の昭和七年のところを見ると一月三十日号のトップというのは、定価販売の緩和にほとんど九割賛成という記事があります。今の再販制の弾力的運用と同じようなことをここで言っています。このころの定価販売というのは出版業界が自発的に作った制度で、別に法律的な規制はなかったのです。定価販売がいちばんいいということを体験的に出版界は知って、定価販売制度を作るのですが、それがきついということで、むしろ定価販売を少し緩和した方がいいのではないかという意見が出てくる。それに九割が賛成しているということです。さらに『出版通信』の囲み記事を見ると、そのことについて各界に意見を求めるということをやっています。この記事などは今読んでも非常に参考になります。
それから、出版というメディアは、今でも人間的要素が非常に強いのですが、『出版通信』や『出版同盟新聞』を読んでいますと、やはりその点での濃厚さが感じられます。昭和十六年一月十日号の死亡記事に、長坂金雄氏夫人の葬儀まで書いているのです。その末尾が、「同三十日午後一時より二時までの間自宅にて告別式をしめやかに執行す。多数の会葬者により、限りなき哀愁の涙が注がれた」とあります。いかにも人間臭い書き方です。
戦時体制へと移行する出版業界
植田: 日配については荘司徳太郎さんなどが書いておられますが、ああいう完成された本で読むよりも『出版同盟新聞』でプロセスを追う方が、非常に実感があります。また、ディテールがわかります。
小林: 日配については、清水文吉さんの『本は流れる』や清水さんと荘司さんの共著の『日配時代史』もありますが、いづれも日配に対する哀惜の色が強いのです。『出版同盟新聞』では、その辺がかなりドライというか、突き放して書いています。しかも、時々刻々の状況を追っていますから、その意味ではすごくおもしろいと思いました。
植田: 日配の問題を含めて戦前戦中の出版業界を知るためには『出版同盟新聞』をきちんとおさえておかないとわからないのだという印象を受けました。荘司さんや清水さんの著書の場合、書くというプロセスのなかで著者自身が取捨選択をおこなっています。当然省いている部分があります。その省いた部分が『出版同盟新聞』にはあるのです。
それから、吉田さんが解説のなかで指摘していますように昭和十年代の出版新体制のきっかけになったのが、電力を始めとする産業統制です。政府は産業を新体制にもっていく一つの対象として電力を統制しました。あの辺のあたりについて、お話しいただけませんか。
吉田: 満州事変が起こりその後中国と全面戦争になりました。昭和十二、三年ごろから、国会でも電力国家管理法とか国家総動員法という法律ができ、昭和十六年以降主に物資の統制のため鉄鋼、石油、石炭などの重要産業については、統制会というものができてきます。電力もそうです。生産、流通、配給の一元化ということでずっと推し進められてきます。
出版界も昭和十五年十二月に、日本出版文化協会、通称「文協」ができますが、その前に昭和十四年ぐらいから業界統制が顕在化し、国策協力のための自主的な集まり、団体として出版中央連盟とか出版懇話会などができてきます。時局に即していえば、昭和十五年夏に第二近衛内閣が成立し近衛新体制運動がありました。そこで紙の統制機関として内閣に新聞雑誌用紙統制委員会ができました。それが結局は出版団体の方に統制事務の権限を委譲し統制するようになるのです。
業界紙も出版新体制に呼応して、昭和十五年二月に帆刈芳之助が主宰していた『出版研究所報』、丸島誠主宰の『出版通信』とあと一紙『出版文化通信』の三紙が合同して『出版同盟新聞』が創刊されます。私はこれを四者一体の具現化した新聞である思います。版元、取次、書店の三位一体から、政府当局による国策遂行のための監督指導のもとに出版統制団体がつくられ、四者一体ともいえる状況がつくりだされます。『出版同盟新聞』はこのための機関紙的役割も担ってくるのです。『出版同盟新聞』の主な書き手は帆刈さんと丸島さんのおふたりですが、オピニオンの部分は帆刈さんが書かれていたように思われます。
小林: 帆刈さんが年長者で丸島さんをリードしていたようです。それと、ふたりには微妙な考え方の違いがあったようです。
吉田: 小林さんは思想の違いがあるとおっしゃいましたが、確かにそういうところは感じます。帆刈自身が廃刊の辞でいっているのですが、日本出版文化協会の改革こそが『出版同盟新聞』のもっとも力を注いで取り組んだ問題であるということでした。
文協ができてからは、出版物の事前審査と用紙配給をセットにして出版の許諾を行なう。さらに日配の創設により配給・物流の統制を含む三位一体の統制を実施していきます。帆刈は配給の問題についても、業界のことを文協の人間は知らないのではないかとかなり手厳しくいっています。読んでいてもおどろおどろしい見出しが並びます。
文協についていえば、発足して一年ぐらいは表立ってもめてはいませんが、二回目の総会は、機構改革をめぐって荒れに荒れました。平凡社の下中弥三郎などが文協改革派の急先鋒でした。問題となったのは、文協の専務理事が新聞界から出たことでした。朝日新聞の出版局長が専務理事に就任したことです。
当時は情報局が大元締めでいろいろなことをやっていましたが、情報局を通じて、新聞社系の人間が出版行政に広く携わってきたのです。専務理事が朝日と兼任していたということで、業界でも不満がありました。昭和十七年八月には、朝日新聞の出版の実績が一番多いということで最大の用紙の割り当てを受けました。当時の用紙の割り当てというのは実績主義でしたが、これは驚きだという、同盟通信のコメントなども出ており大論争になっています。新聞社出版局の文協加盟問題などももめたことです。帆刈はこの専務理事排斥の論陣を張っいます。
このようなことがあってか、昭和十七年七月に『出版同盟新聞』は印刷所へ印刷中止勧告を出されてしまいました。発行元にではなく、印刷所に出されたのです。帆刈はひるまずに情報局へ行き中止勧告の撤回を求め、業界内にも声援の声が飛びました。何故こういう通達が情報局から出たのかというと、『出版同盟新聞』は文協にも印刷協会にも入っていないにもかかわらず、用紙を得ているのはどうしてかということを調べたて、ついでに印刷中止を勧告することになったのです。驚くべきことに五百連以上の用紙の手持ちがあったのです。おそらく『出版同盟新聞』の姿勢に共感し用紙を提供してくれる支援者があったのでしょう。この時も、帆刈は「新聞精神の復興だ」と毅然といっております。
その後も文協職員による用紙の横流し問題などを取り上げ、文協改革報道をおこなっています。こういうものを読んでいくと、『出版同盟新聞』が業界に信用されていて、それでいろいろな情報をもらって報道していたということがわかります。
昭和十八年二月に国家総動員法に準拠して事業ごとに事業統制が行われていくことになります。出版統制団体日本出版会が発足していくのです。六月には『出版同盟新聞』も東京都下の各種業界紙すべてが廃刊という方針が出て、六月二日号で廃刊になりました。帆刈と丸島の廃刊の辞というものが最後にあります。
三紙合同と堅持した報道姿勢
小林: 出版界は反権力か、体制順応型の故であるかはわかりませんが、戦争中の政府あるいは情報局に対しての姿勢が一貫していないというか、むしろいいかげんだったといういい方さえできるぐらい変わり身の早さがあります。
その点、帆刈さんは一貫していたと思います。しかし全部一貫すると自分の身が危ないのです。当時は軍部に睨まれると兵隊として引っ張られます。二等兵で召集されて、ガタルカナルなどに放り込まれては元も子もないのです。それぐらいの権力を当時の軍部は持っていたのです。四十歳代でも召集しました。そういう危ない時代の中でギリギリの抵抗をしていたのではないかと思います。しかも一業界紙です。いま『出版同盟新聞』を読むと、この辺がああいう危険な時代のジャーナリズムの限界だったのかという思いがします。今の時代の人は、かっこよく突っ込めということを言うけれど……。媒体がつぶれては報道し記録して残すことはできません。
植田: 昭和十六年の二月五日号に「出版新体制と現状維持」という一文があり、「英米の現状維持論を叩きのめして国際新体制をしくのが日独伊枢軸の勧告であることはわかっているが、それは国際関係のことであってこれをそのまま出版新体制にもってくるとあてはまることとあてはまらないことがある」と書いています。微妙なバランス感覚というものを感じながら読みました。
小林: 政府、軍部に対して、特に軍部というのは武器を持っているのですから、いつ殺されてもおかしくはないのです。暗殺の実例などいくらでもあります。今読み返すと、ギリギリまで吠えていて、何か涙ぐましい感じです。昭和十八年での廃刊は、紙の事情などもあったと思いますが、自由な言論・報道を旨とする新聞の使命としてもあの辺が限界ではなかったのでしょうか。
植田: 本当に危ないバランスの上に立ちながら、伝えるべき客観的事実はきちんと報道し、論評もきちんと計算をしながらしている。そのバランス感覚があるため、昭和十年代の出版史を検証するうえで、この新聞を資料として使えるのだと思います。
吉田: これは小川菊松さんの著者に出てくるのですが、結局は日本出版会発足のころまでに、三千六百社あった出版社が二百社ぐらいまでに整理統合されようとしているのです。その過程には、やはり何かしらの体制順応があったり、何らかのメリットを得ていたのだという点は、この資料を見て思われます。どうしても一九四〇年代の出版研究というのは、社史と回想がメインなのです。回想というのは、先ほどの日配関連の本の話しでもありましたが、やはり、思い込みや推測、自己弁護的な面があります。その点、時代的な制約はありますが、状況がヴィヴィトに記述されています。
ーー最後に『出版通信』『出版同盟新聞』の現代史的意義についてお伺いしたいのですが。
吉田: 先ほども申しましたが、業界紙でしかも一ヶ月に五回ないし八回ぐらい出たこともあります。時々刻々、そのときそのときを切り取っているのです。後になって、学者や研究者のようにじっくり考えて、その時代それはどういう意味があったかというようなことを考える暇もなく、とにかく事実報道が優先でした。刻刻として事実報道をしてきたのです。それが、時間が経てば経つほど貴重な記録だと私は思います。今、まだ私自身が気づいていないことが、十年後に資料を読んだときに、あらためてああそうだったのかという気のつき方をする原資料だと思います。あやふやな部分もあるのですが、あやふやな部分があるだけに非常に生なものが出ています。よく資料として残しておいてくれたと思います。