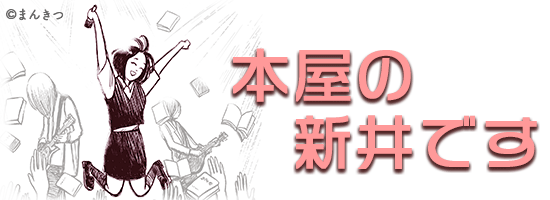ディストピアといえば、小説読みにとっては、文学の魅力的なカテゴリのひとつである。理想郷とはかけ離れた近未来が、空想の絶望ではあっても、現実社会の延長線上にあるように感じてならなかった。そして先日、西の方へ旅に出た際、ついに片足を突っ込んでしまったのである、ディストピアに。
その商店街には、入口にチェーンの書店が構えており、そこそこ賑わっていた。しかし、数十メートル先にも書店があり、こちらにはお客の姿がない。
入口には最新の週刊誌が平積みされているが、右の壁面を見ると、骨董品のような旅行ガイドが面陳されている。年度は7年前のもので、もはや朽ちかけていた。反対側には、背表紙が焼けすぎて何才児用かも判別できないドリルが並ぶ。子どもに買い与えたら泣くだろう。中央を遮るのは文庫の棚だが、土石流が通り過ぎたかのようにこってりと埃が積もり、とても手を伸ばせる代物ではなかった。
そして店の突き当たりには、店主とおぼしき男性が、テレビを見ている。町の本屋さん然とした、穏やかそうなおじさんだ。ただ、店に恐る恐る入ってきた私に、ぴくりとも反応しない。どちらかがもう、死んでいるような気がした。
(新井見枝香/HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE)
(2019年10月31日更新 / 本紙「新文化」2019年10月24日号掲載)