-
 連載記事
連載記事
第83回 まだまだある本屋の役割
今年度は、公共図書館の様々な集まりで話をしてほしいという依頼が急増した。7月の図書館問題研究会による第70回全国大会茨城大会in日立の分科会「図書館員だから本気で書店と出版業界を理解する!」をスタートに、山形県新庄市や岩 […] -
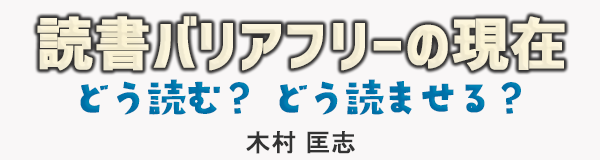 連載記事
連載記事
第4回 本を音で読む・前編
出版物の音声化には、大きく分けて、人が読む方法と、音声合成を利用する方法がある。前者には、主に出版社が刊行し、ストアで販売され、一般読者が楽しめるオーディオブックと、主にボランティアにより作成され、公共図書館・点字図書館 […] -
 連載記事
連載記事
第8回 貸本所に代わり人気呼んだ「貸与店」
韓国で「貸与店」(漫画貸与店)と呼ばれるレンタルショップが登場したのは、1988年頃とされる。貸与店の増加は、従来型の貸本所(漫画房)の減少と対照的だった。 貸本所は主に「店内で読む」、店によっては「店外貸出」もする業態 […] -
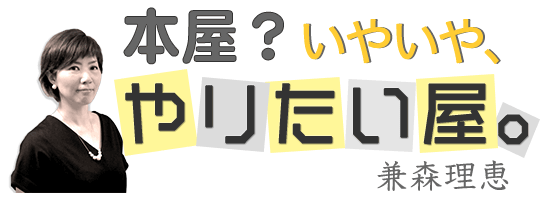 連載記事
連載記事
第29回 子どもに還る場所
歯医者さんが好きだ。伯父が歯科医で子どもの頃から診療室は馴染の場所だ。診察用の動く椅子もロボットみたいでワクワクしたし、何より、伯父に溺愛されていたので、診療所は子どもの私が甘やかされる場所だった。 高校生になると、伯父 […] -
 連載記事
連載記事
第82回 島で本を買う
GW明け、与那国島を訪れる機会をいただいた。与那国島は、南西諸島八重山列島の島で日本の最西端に位置する島であり、いわば国境の島である。「Dr.コトー診療所」のロケ地となった島として記憶されている方も多いのではないだろうか […] -
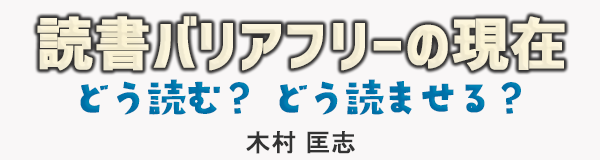 連載記事
連載記事
第3回 「本」に選択肢を
バリアフリーでアクセシブルな出版物がどのようなものであるべきなのかは、読書困難者の「困難」がどこにあるのかにより変わるため、簡単に集約することはできない。すべてをカバーする最適で単一のかたちはない、ということだ。 紙の本 […] -
 連載記事
連載記事
第81回 本屋の役割
今朝の読書タイムは、未来屋書店さんが発行する、未来の読書家を育むための本と本屋の案内誌「みらいやの森通信」だった。 「未来の読書家を育む」ことを目的に、未来屋書店プレミアムサービスを開始するというお知らせが掲載されていた […] -
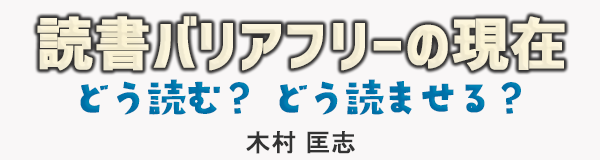 連載記事
連載記事
第2回 読書バリアフリー法とは
「読書バリアフリー法」、正式名称「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施行されたのは2019年。「読書環境の整備」とあるくらいだから、出版に携わる者なら知らずにいることはできないはずだが、施行後4年以上が経 […] -
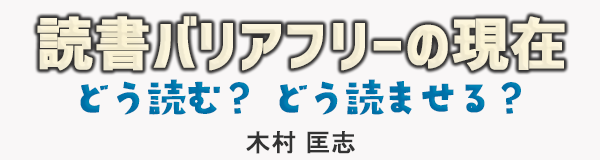 連載記事
連載記事
第1回 「ハンチバック」の衝撃
〈読書文化のマチズモを憎んでいた〉〈「本好き」たちの無知な傲慢さを憎んでいた〉--昨年、第169回芥川賞を受賞した市川沙央さんの『ハンチバック』(文藝春秋)に登場するこのくだりに衝撃を受けた「本好き」は少なくないだろう。 […] -
 連載記事
連載記事
第80回 今、必要な本
嬉しい出来事があった。穂高明『これからの誕生日』(双葉文庫)が刊行から10年経って重版され、再び読者に届けられるというお知らせがあったのだ。 本書の主人公は、バス事故から一人だけ生き残った千春という少女だ。当事者でない人 […] -
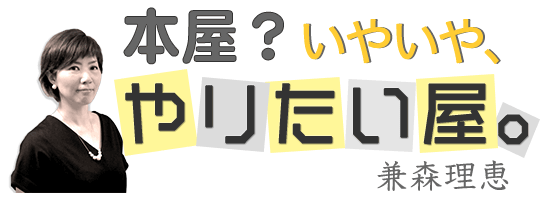 連載記事
連載記事
第28回 欲にまみれた言葉
人気のドラマの影響もあってか、「不適切」ということについて、このところやたらと考えさせられる。パワハラやセクハラ、された人が嫌だと思ったらそれはもう不適切な行為。けれど、それってとっても曖昧だし、ことにそういうことをして […] -
 連載記事
連載記事
第7回 80~90年代雑誌漫画の隆盛と失速
韓国では1950年代に漫画専門誌が創刊されたが、その後はしばらく途絶え、子どもや大人向け雑誌の一角を漫画が占めるに留まっていた。 「ほぼ漫画だけの雑誌」は、82年創刊の「宝島(ボムルソム)」が500頁前後のボリュームで […] -
 連載記事
連載記事
第79回 「蔵と書」
スマホでなんでも手に入るこの時代に、紙の本にこだわり頁をめくる時間がもたらす価値とは何だろうか。本屋に関わる仕事しているにも関わらず、忙しさを言い訳に考えることを止めてしまっていた問いである。 大阪に生まれ名古屋で育った […] -
 連載記事
連載記事
第78回 書店振興PT発足に際して
ネット通販や電子書籍の普及などを背景に全国的に書店が減少するなか、3月5日に経済産業省は、地域の書店の振興に向けた部局横断のプロジェクトチームを立ち上げた。新たな支援策を検討していくことを発表し、まずは書店の現場から実態 […] -
 連載記事
連載記事
第6回 ウェブトゥーンヘの誤解と〝工場漫画〟
2010年代末以降、韓国ウェブトゥーンは「分業体制のスタジオ制作」という新しい手法で漫画を制作していると、日本では報じられた。だがスタジオ制作漫画は、必ずしも「新しい」わけではないし、「ウェブトゥーンではスタジオ制作が主 […] -
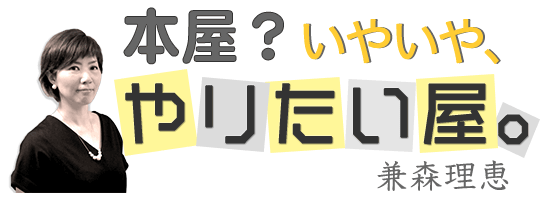 連載記事
連載記事
第27回 日常にひそむ不思議
春一番が吹き荒れたある日のこと。強風のせいで遅延している電車はなかなか進まない。やっと次の駅に着いたと思ったら、「バチン」と車内が真っ暗になった。アナウンスもない。しばらくすると何事もなく灯りがつき、電車は扉を閉めると走 […]
