-
 連載記事
連載記事
第15回 国語教育と読書
過去20年の子どもの読書推進に関して、カギとなる出来事や法律の流れを調べていた。 2000年「子ども読書年」、01年「子どもの読書活動の推進に関する法律を公布・施行」、04年「これからの時代に求められる国語力について […] -
 連載記事
連載記事
第14回 ローカル、ガラパゴス
4度目の緊急事態宣言発出。日々の新規感染者数の増減に一喜一憂することもなくなってしまった。昨年に続き今夏も墓参りの帰省ができないことが確定し、少々落ち込んでいる。いつになったら岩手の実家に帰ることができるのだろうか。 […] -
 連載記事
連載記事
第13回 その行為は読書である
6月は、集中的に「毎日新聞2020年度読書調査」の資料を精読する作業を行っていた。そのなかで、気になった調査結果があった。 「雑誌を読むこと」38%、「漫画を読むこと」31%、「本を立ち読みすること」17%、「本を朗 […] -
 連載記事
連載記事
第12回 今の消費者、これからの読者
書評誌「本の雑誌」初の10代向けのブックガイド、『10代のための読書地図 別冊本の雑誌20』(本の雑誌社)が6月下旬に出版される。 公開された目次を見ると、朝の読書や夏休みの読書感想文に対応した「本の雑誌が選ぶ10代 […] -
 連載記事
連載記事
第11回 次のステップ
図書館の蔵書を電子データ化し、メールで利用者に送信することを可能にした改正著作権法が、5月26日に参議院本会議において全会一致で可決成立した。 出版界もいよいよ次のステップに進んだな、と思いつつ、その後の世界を妄想し […] -
 連載記事
連載記事
第10回 若者たちの掌
NHK放送文化研究所の調査によると、10代から20代の若者の約半数がほぼテレビを見ないという。 新聞や本と同じように、若者のテレビ離れも進んでいることになる。テレビは若者にとって、日常的に情報を得るメディアではなくな […] -
 連載記事
連載記事
第9回 地域コミュニティの拠点
3月、4月と立て続けに茨城県で新しい本屋が誕生した。いずれも地域コミュニティの拠点をつくろうという地元住民の想いから生まれた本屋だ。 ひたちなか市の「然々書房」(ぜんぜん~)は、ライブラリー・カフェ然々の店内で3月に […] -
 連載記事
連載記事
第8回 出版不況の出口
書店調査会社のアルメディアによると、2020年5月時点での書店数は1万1024店で、前年比422店減少したとある。さらに、店舗をもたない本部や営業所などを除くと、その数は9762店で前年比412店減少という調査結果が発 […] -
 連載記事
連載記事
第7回 本の新たな居場所
山形県の山間部に位置する、人口約1万1000人の町に住む方から突然連絡があった。 「(前略)先週、中山町唯一の書店がなくなりました。どうしてもこの町に本屋を復活させたいです。地域の仲間とともに小さな規模でもいいから、 […] -
 連載記事
連載記事
第6回 記録と記憶
東日本大震災発生から10年。節目ということもあり、様々な媒体から震災関連の取材と執筆依頼をいただいた。今年に入ってから、被災地の書店さんの声を聞き、多くの震災関連本を読む機会が多かった。 残された者を守ろうとする優し […] -
 連載記事
連載記事
第5回 シェア本屋、シェア図書館
近年静かに広がっているシェア本屋やシェア図書館を運営する方々のお話をうかがう機会が増えた。まちに本屋が在ることの意味や意義を、あらためて考えるきっかけをもらっている。 知人が、岩手県盛岡市の介護施設と図書館を融合させ […] -
 連載記事
連載記事
第4回 これからの読者のために
本と読者のコミュニケーションを双方向からサポートすることを目的として、昨年、同志数名と「未来読書研究所」という団体を設立した。 GIGAスクール構想で進む学校教育のデジタル化が読書に与える影響の調査、幼少期から小中高 […] -
 連載記事
連載記事
第3回 まちには本屋が必要だ
かつてまちに一軒だけあった本屋を閉じ、無書店地域の一つをつくった時から、いや、それ以前からそう思い続けている。 業界の隅に身を置く者として、無条件に「本屋は素晴らしいのだ」というつもりはないが、本と読書を通じて得るこ […] -
 連載記事
連載記事
第2回 出合いの蓄積
「読書欲は、読みたい本との出合いの蓄積から生まれる」僕の活動のベースとなっている言葉だ。 読書の楽しみは、読者が自分で本を選択するところから始まる。そう、自分で本を選ぶ楽しみと喜びもまた、読書の一部と言えるだろう。本 […] -
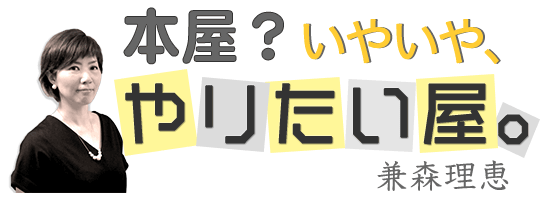 連載記事
連載記事
第6回 会いたくなる人
出勤前、土日祝日は必ず二重橋前のローソンに寄る。彼がいるからだ。商品は必ず両手で受け取り「ポイントカードはございますか? お支払いは? はい、PayPayですね。はい、コードを真ん中に合わせて……(バーコードに機械をか […] -
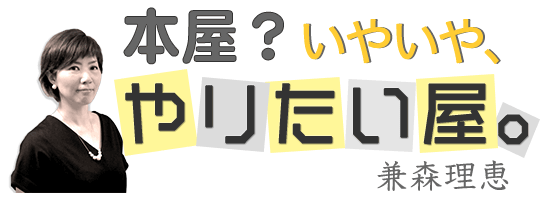 連載記事
連載記事
第5回 祖母との思い出
私を本好きにしたのは、まぎれもなく祖母だ。祖母のことが大好きだった。祖母の好きな食べ物は私の好きな食べ物。祖母の好きな色は私の好きな色。 カクセイイデンという言葉が好きだった。「理恵ちゃんとおばあちゃまはカクセイイデ […]
