-
 連載記事
連載記事
第111回 書店員参加の司書研修会
昨年、政府の骨太方針に初めて、「書店と図書館等との連携促進等を含む文字活字文化の振興」が盛り込まれてから、NPO法人読書の時間では、各自治体の公共・学校図書館関係団体からの書店との連携についての講演依頼が増え続けている。 […] -
 連載記事
連載記事
第22回 日本マンガをめざす韓国の作家たち
2000年代初頭には、韓国の漫画家が次々に日本のマンガ雑誌で連載する流れがあった。だが2000年代後半になると、韓国国内では青少年や大人向けの紙漫画の凋落および、ウェブトゥーンの隆盛が決定的になり、日本をめざす漫画家は激 […] -
 連載記事
連載記事
第110回 住民のメリット考え連携を
6月末の福島県高等学校司書研修会県大会から、今年もNPO法人読書の時間の自治体行脚が動き出すことになる。 ありがたいことに、今年も全国各地の図書館・学校図書館関連団体からお声がけいただいている。昨年に引き続き、お題はすべ […] -
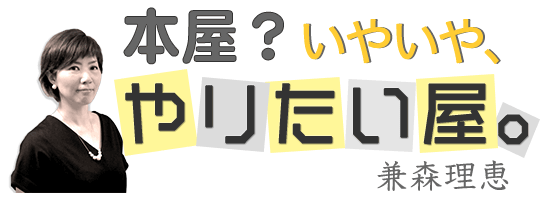 連載記事
連載記事
第43回 視線の先に広がる未来
先日ブロンズ新社さんの新刊説明会があり、全国から書店員が集まった。丸善ジュンク堂書店のそれぞれの地区の児童書担当者とも久々に会うことができた。コロナ後こういった機会が減っているので、本当にうれしい。作家さんのトークや新刊 […] -
 連載記事
連載記事
第109回 活性化プランのポイント
6月10日に7省庁および機関の連名による「書店活性化プラン」が発表され、骨太の方針でもこのプランの推進が盛り込まれた。 これに基づく施策として、文部科学省と文化庁は、地域における文学・活字文化振興モデル構築事業や、図書 […] -
 連載記事
連載記事
第108回 なぜ本屋か本なのか
貸本屋として生計を立てるおせんの〝お江戸出版界捕物帳〟第2弾『往来絵巻 貸本屋おせん』(高瀬乃一/文藝春秋)が発売された。 女手ひとつでおせんが営む「梅鉢屋」は、店舗を構えず、振り売りや棒手振りと同様に、お得意先をまわり […] -
 連載記事
連載記事
第21回 大手PFの支配と「独立漫画」の挑戦
NAVER Webtoonで個人作家が連載権を獲得するには、自由投稿の「挑戦漫画」で人気を博したあと、「ベスト挑戦」「公式連載」と勝ち上がっていくのが一般的だ。最初の「挑戦漫画」には分量や更新頻度の制約がないが、公式作家 […] -
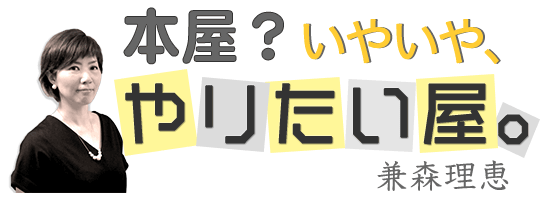 連載記事
連載記事
第42回 自惚れと戒めのつぶやき
はるちゃんが久しぶりに店に来た。私の一番若い友だち。友人の娘さんなのだけれど、子どもが苦手な私が唯一仲良くさせてもらっている女の子。出会った頃は4歳だったはるちゃんも、なんとこの春から高校生。お店には大学生になったお兄ち […] -
 連載記事
連載記事
第107回 吉成信夫氏の新刊に学ぶ
元ぎふメディアコスモス総合プロデューサーの吉成信夫さんの新刊『賑わいを創出する図書館 開館9カ月半で来館者100万人を達成した「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の冒険』がKADOKAWAから6月23日に発売される。 ぎ […] -
 連載記事
連載記事
第106回 文庫復刊で旬を生み出す
大日本印刷(以下、DNP)が2月から、書店が売りたい本を生み出せる〝未来の出版流 通プラット フォーム〟構築の取組みを開始し、その第1弾として5月から「DNP復刊支援サービス」の提供を始めた。 全国の各地の書店には、1冊 […] -
 連載記事
連載記事
第20回 「韓国コンテンツは国策で成功」論の虚妄
「韓国のエンタメ、コンテンツ産業は国策で成功している」という論調が、日本には根強く存在する。ウェブトゥーンもそのひとつだと言う人がときどきいるが、それは的外れな見立てである。 日本の文化産業支援政策と比べれば、韓国のほう […] -
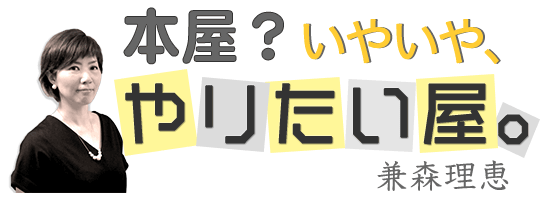 連載記事
連載記事
第41回 再会のおてつだい
EHONSのInstagramに中文の長いメッセージが届いた。通販や海外発送のお問い合わせがほとんどなので、今回もその類だろうと思っていたが、それにしては長文だ。ChatGPTに翻訳してもらう。 「こんにちは。私は台湾か […] -
 連載記事
連載記事
第105回 「ひな型」改訂、課題の把握を
4月10日、新文化オンラインが「再販契約書ひな型、第六条2項『官公庁等の入札に応じて~』を削除へ」と題した記事を掲載した。 出版4団体で構成する出版再販研究委員会は同日、再販売価格維持契約書のひな型のうち「取次|小売」間 […] -
 連載記事
連載記事
第19回 〝韓国は日本マンガの海賊版だらけ〟の誤解
ウェブトゥーンが流行する以前、日本ではしばしば「韓国漫画は日本のパクリや海賊版だらけ」だと語られてきた。本稿では、その点に関する誤解を解いておきたい。 韓国で外国の著作物が保護対象になったのは、1987年の著作権法改正以 […] -
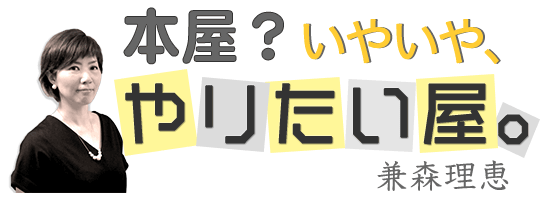 連載記事
連載記事
第40回 祝第40回!!
しつこいようだが、1月のブリベヤ旅行の話に戻らせてほしい。旅行最終日、私とCちゃんは1本の電話を待っていた。路面電車のなかで、Cちゃんの電話が鳴る。予定時間より早い。 「獲ったよ」 Cちゃんのアイコンタクト。私はらいおん […] -
 連載記事
連載記事
第104回 教科書販売〝条件〟の再考を
全国の外商をおもちの書店の皆さん、一年で一番の繁忙期である教科書シーズン、お疲れ様でした。今年も無事に子どもたちに教科書をお届けすることができて、ほっと胸をなでおろしております。毎年のことながら、教科書供給の目途が立つと […]
